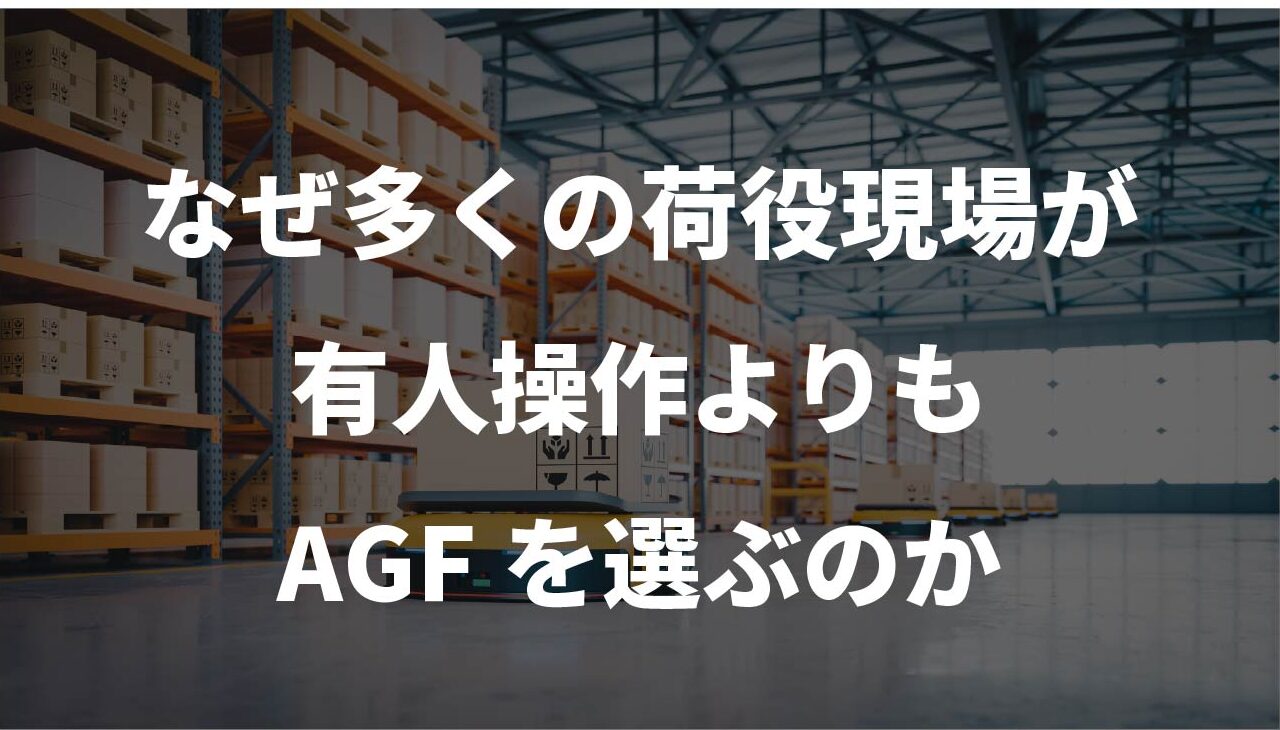物流業界を支えるTMS(輸配送管理システム)とは?

物流業界では、効率的な輸送管理が重要な課題となっています。近年、その解決策として注目されているのがTMS(Transport Management System)です。TMSは日本語で「輸送管理システム」または「輸配送管理システム」と呼ばれ、物流の効率化に大きな役割を果たしています。本記事では、TMSの概要から機能、メリット、導入時の注意点まで詳しく解説します。
TMSの基本概念と役割
TMSとは、Transport Management Systemの頭文字をとった略称で、商品が荷されてから配達完了までの輸配送をトータルで管理するシステムです。物流における輸送プロセスを効率化し、配車業務の管理や貨物の追跡などの機能を提供します。
TMSは配車計画や運行管理を支援する輸送・配送に特化したシステムであり、医療分野で使用されるTMS(磁気刺激治療)とは全く異なるものです。物流分野では、限られたリソースを最大限に活用し、効率的な輸送を実現するために不可欠なツールとなっています。
WMSとの違い
物流分野では、TMSと並んでWMS(Warehouse Management System:倉庫管理システム)も重要なシステムです。両者の違いを理解することは、物流システムを検討する上で重要です。
WMSは倉庫内の物流業務を管理し、入出荷する荷物の管理やリアルタイムな在庫状況の管理、帳票や請求書の発行などの機能を持ちます。一方、TMSはトラックの配車を中心に輸配送の進捗管理など、輸送プロセスを対象としています。
両システムを連動させることで、商品の入荷から配達までの流れを一気通貫で効率的に管理することが可能になります。
TMSの主な機能
TMSは様々な機能を備えていますが、主に以下の機能があります。
配車業務の管理機能
配車業務の管理機能は、荷物を運送会社および車両に割り当てる配車業務を支援します。この機能では、荷物の輸送に最適な運送会社やトラックの種類、輸送温度帯、輸送モード(貸切・混載)などを選定します。
輸配送には様々な条件や制約が存在します。例えば、荷物のサイズ・重量・温度帯や、届け先の場所・時間帯・車両・待機・納品方法などの「軒先条件」と呼ばれる細かな取り決めがあります。TMSはこれらの複雑な条件とトラックの空き情報を組み合わせ、適切な計画を立案することをサポートします。
システムによっては、自動配車機能や自動積み付け機能も備わっており、配送順やルート、荷物の予定到着時刻などを容易に算出することが可能です。
貨物の追跡機能
貨物の追跡機能は、荷物の輸送中の状況をリアルタイムで追跡する機能です。「中継」「配達」などのポイントとなる輸送イベントをトラッキングし、トラックがイベントを経て「配達完了」となるまでの進捗を追跡します。
スマートフォンや車載器を活用して輸配送状況を可視化したり、GPS機能を使って位置や状況(運転中・休憩中・停止中)を把握することができます。さらに、デジタコ(デジタルタコグラフ)やドラレコ(ドライブレコーダー)を使うことで、車両およびドライバーの運行状態(燃費、安全運転など)も管理できます。
この機能により、トラブルが起きた際に遅れが大きくならないよう迅速に対処できるほか、顧客からの問い合わせにもスムーズに対応できるようになります。
その他の機能
TMSには上記の主要機能以外にも、以下のような機能があります。
- 運転日報作成機能: 各車両の走行データなどからドライバーそれぞれの日報を自動で作成する機能です。この機能によりドライバーの業務負担が軽減されます。
- 運賃計算機能: 冷蔵車・冷凍車といった特殊車両割増や休日割増、深夜・早朝割増などの割増運賃も考慮し、配送拠点から届け先までの運賃を正確に計算する機能です。
- バース予約機能: 工場や倉庫にある配送する荷物の積み下ろしを行う「バース」の予約を管理する機能です。この機能により、バースの混雑が緩和され、トラックの待ち時間が減少します。
TMSを導入するメリット
TMSを導入することで、様々なメリットが得られます。
積載率の向上
TMSを活用することで、精度の高い配車計画が立案でき、積載率が向上します。ドライバーの人材不足が深刻化する中、限りあるトラックの有効活用は極めて重要です。
最適な配車計画を実行することで、無駄な輸送が減少し、CO2の排出量も抑制できるため、環境負荷への配慮にも寄与します。
配車業務の標準化
配車業務は従来、ベテランの配車担当者の経験やノウハウに依存しやすい属人的な業務でした。TMSを導入することにより、配車業務が標準化され、属人的な業務から解放されます。
ベテラン担当者の「頭の中のロジック」が「システム設定」に代替されることで、誰でも精度の高い配車ができるようになり、人的ミスの削減も期待できます。
配送状況の可視化
TMSでは、ドライバーの稼働状況に加えて荷物の配送状況も可視化できます。輸送会社に「いつ到着するのか」などの問い合わせがあった際、システムを通じて即座に確認可能となり、ドライバーへの確認が不要になります。
さらに、配送状況がインターネットを介して届け先を含む関係者全員に共有されていれば、知りたい人が自分で調べることもできます。可視化された情報はKPI指標として業務改善にも活用できます。
物流コスト削減
配車を自動的に最適化することで、車両の数を最小にすることができ、ドライバーの人件費を削減することができます。また、自動で配送ルートも最適化してくれるため、燃料費や運賃についても必要最低限で済ませることが可能になります。
さらに、システムで物流コストを見える化することにより、改善可能な部分が明確になります。
TMSの導入における課題とデメリット
TMSの導入には多くのメリットがありますが、いくつかの課題やデメリットも存在します。
導入コストと手間
自社に合ったTMSを導入するには多くのコストと手間がかかります。自社の強化が必要な部分を分析したり、ニーズを把握したりする必要があります。
また、TMSの設備を導入するには多大な費用がかかり、費用対効果を出すのに時間がかかる場合もあります。
サービス浸透の時間
TMSを導入すると物流システムに大きな変更があるため、全社員への研修が必要となり、社内でのサービス浸透に時間がかかることがあります。新しいシステムに対する抵抗感や習熟に時間を要する場合もあるでしょう。
TMSの選び方のポイント
TMSを選ぶ際には、以下のポイントを考慮することが重要です。
- 自社の課題やニーズの明確化: 自社をどのように改善していくかのビジョンを明確にし、強化すべき機能を特定することが必要です。
- 導入形態の確認: クラウド型かオンプレミス型か、自社の状況に適した導入形態を検討します。
- 必要な機能の確認: 配車管理、貨物追跡、運賃計算など、自社に必要な機能を確認し、それらの機能が備わったTMSを選びます。
- サポート体制の確認: システム導入後のサポート体制も重要な選定ポイントです。
結論
TMSは物流業界において、輸送プロセスの効率化や可視化、コスト削減など多くのメリットをもたらす重要なシステムです。ドライバー不足や環境問題など物流業界が直面する課題を解決する一助となり得ます。
導入にはコストや手間がかかるものの、長期的に見れば業務効率化やコスト削減などのメリットが大きいといえるでしょう。自社の課題やニーズを明確にし、最適なTMSを選定することが成功への鍵となります。
物流DXが進む現代において、TMSは単なるシステム導入ではなく、物流戦略の一環として位置づけることが重要です。今後も技術の進化とともにTMSの機能は拡充し、物流業界の発展に寄与していくことでしょう。
物流のDX化はL&N JAPANにお任せください!
L&N JAPANは、これひとつで工場内のすべての業務プロセスをデジタル化できます。

- 会社紹介
- L&N JAPANができること
- 製品一覧